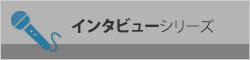「人材が育つ組織をどうつくるか②―
メンター制度の果たす役割」
松下信武(ゾム株式会社代表取締役)×留岡一美(POLARIS Partners代表)
「人材が育つ組織をどうつくるか①―エグゼクティブ・コーチングの果たす役割」から続く
どういう局面でコーチングがもっとも必要とされるのか
留岡 コーチングがどのような局面でもっとも必要とされるか、ということを考えたときに、海外赴任の前などに行う「異文化適応のためのコーチング」というのが一つありますが、それ以外にはどういった局面でしょうか。
松下 エグゼクティブ・コーチングの場合、とくに外資系企業では、「昇進」の局面で行われることが多いですね。昇進したときが、コーチング導入の一つのきっかけになっています。ステージが変わったら、必要とされる能力が変わってきますので、そこを補うためにコーチングを使うことが多い。一方、日本企業では、「困っているとき」が多いです。何かトラブルが起きているとか、「どうみても彼は今、行きづまっているよね」というときに使われることが多いです。
それから、ある人の下で部下が育っておらず、「あの人の下にいくと、全員つぶれてしまう」というとき。プレイヤーとしては優れた人だったけれど、マネージャーとしては問題だ、という場合です。課長のときと部長のときでは要件が違います。マネジメント能力の不足といった「谷間」で、コーチングを要求されることが多いですね。ただ、今後は少し違ってくると思います。やはり、世界との戦いになってきますので、戦い方が変わってくる。「あの戦い方ではとてもやっていけないよね」ということがこれから出てくると思いますので、そこでのコーチングは必要とされるでしょう。
留岡 それは私も注力したい分野です。もう一つ、最近の傾向として役員会ガバナンスの乱れが顕在化してきています。社外取締役を置くことを法制化する動きがありますが、そんな付け焼刃で改善される問題ではありません。ボードメンバーのガバナンス能力開発、とくに新任の取締役に対する教育をどうするかという課題への対応も求められています。
松下 そうした場合、コーチングのやり方を変えないといけないのだろうなという気がします。いわば、ethics(倫理)の問題です。倫理の問題を、単なる対話によって扱えるかどうかという問題があります。本来は、ボードメンバーに高い倫理観をもたせようと思うと、課長くらいから教育しておかないといけない。一朝一夕には身に着かないですから、役員になってから倫理的なテーマについてどのようなコーチングをするか、ということは我々にとっても大きな課題ですね。
「異文化適応」のためのトレーニング
松下 メンター制度については、のちほど詳しくお伺いしますが、留岡さんがコーチングやメンター制度など、1対1の教育をご自身のビジネスの一つにされようと思ったきっかけは何ですか。
留岡 私の会社POLARISは、日本企業が「開いていく」、「異文化に入っていく」ための支援を行っています。そのときに、団体戦(企業と企業の戦い)の前に、まず個人戦があるだろうな、と思っています。日本のような文化的に同質の環境の中でなく、雑多な環境の中での戦いを通して、自分を開いていくとか、とことん粘る、ということが身についていくと良いのだろうなと思います。日本で普通にしていては身につかないので、ストレッチした環境や、非常に高いダイバーシティの環境に放り込む。そこに1対1のコーチングやメンタ―制度があると、成長が加速する気がします。
私の仕事は、一つは人材育成ですが、もう一つは外部スカウトの仕事です(POLARIS Leaders Link http://polaris-leaderslink.com/)。スカウトの仕事のほうは、成長する環境をつくる、という考え方から始めた側面が強いですね。社内だけでは、いずれ成長カーブが寝てくる時期がくる。環境を変えることにより、限界を打ち破って、新たに大きく成長できる。その一方で、環境が変わると、不安定になるので、そこにコーチング、メンター制度が必要になる瞬間があるだろうなと思いました。
松下 環境変化によって揺らぎを生じさせる。揺らぎが生まれているので、揺らぎの真っただ中にいる本人はそうとう不安になる。そのような場合、ときにはコーチングやメンター制度のようなサポートが有効だと考えておられるのですね。
最近よく、「グローバル化」のためのコーチングを行ってほしい、という依頼を受けるのですがこれは実は非常に難しい。というのは、「グローバル化とは何か」ということが定義されていないと、コーチングの対象にできないのです。少なくとも私の場合は、クライアントの側にきちんとした定義がない場合は、お受けしていません。
そもそも、本来ビジネスは国境を超える性質をもっていますので、ビジネスのグローバル化というのは、自然なことなのではないでしょうか。それゆえ、揺らぎの幅も大きくなり、グローバル化の意味合いが広くなるというか。
留岡 そうですね。まずは、その企業なりの「グローバル化」の定義が必要なのかもしれませんね。当社の提供するサービス全般と、「グローバル化」は密接にかかわっているのですが、当社の場合は、ビジネスにおけるグローバル化のうち、「異文化適応」という面を重視しています。たとえば英語でプレゼンテーションが堂々とできる、といったところまでブレークダウンすると、コーチングや研修も行いやすくなります。
松下 先ほど、社長と社員の間のぶつかり合いが大事だという話をしましたが、もしかしたら、「英語で喧嘩ができる」ことが大切なのかもしれませんね。余談になりますが、グローバル化で歴史上、最初に成功した国はジンギスカンのモンゴル帝国です。もともとモンゴルの位置はシルクロードの周辺にあったので、異文化が絶えず行き来していて、かれらは通行税のようなものを収益源としていました。そして、自国の人数が少なかったから、他国の人を使わざるをえませんでした。「この分野だったらこの国の人」というように、世界中からすぐれた人を連れて来たからモンゴル帝国は強かったと、歴史家の間では言われています。
留岡 参謀にはイラン人を使う、といった具合ですね。
メンター制度の特長
松下 メンター制度について、改めて、留岡さんの関わりを教えていただけますか。
留岡 私自身のキャリアを振り返ると、3-5年で環境が変わって、ということを繰り返し、変わるたびにキャッチアップして一皮むけてやっていきたいな、という気持ちがありました。その3-5年の各タームで、常にメンターがいました。一人のときもあれば同時期に二人のときもありましたが。でも常に自ら求めていき、メンターになってもらいました。その存在が成長を加速させてくれた、という実感があります。それがなかったら、貴重な経験があっても、忙しさにまぎれて、その意義を考えずに素通りしていたんじゃないかな、という気がします。
このような経験があるので、これからそれを還元するというか、メンター制度をつくっていきたいと思っています。松下先生は、メンター制度(メンタリング)をどうとらえていらっしゃるのでしょうか。最近、メンター制度を取り入れている会社がありますが、コーチングとは、目標の立て方や趣旨が少し違うように思うのですが。

松下 私はコーチですけれど、メンター制度がきちんと機能したら、メンター制度はある意味で、コーチングの限界を超えるものだと思います。企業組織のよくないところは、視野が狭くなりがちであるところです。コーチングは、視野を狭くしないとできません。目標を明確にしないといけないので、できるだけ視野を狭くしてあげないといけません。スポーツ選手のコーチングでたとえれば、選手にオリンピック以外のことを考えてもらっては困るわけです。ところが、視野を狭くしていると、時代の変化がわからない。そして、タコつぼ状態がおこりやすい。これらは、ビジネスモデルを大きく転換するときに邪魔になる。そうした広い視野が必要とされる場合、よく機能するメンター制度とコーチングの二つのうち、どちらかを選ばないといけないとしたら、よく機能するメンター制度をとっていただいたほうが、目標達成の確率は高くなります。
留岡 外資系、海外企業のエグゼクティブの場合は、「個人」がまず先にあって、ほうっておいても視野が広いので、コーチングで狭めても、機能するのだろうなと思います。
松下 「視野の広さ」ということにおいて、唐突なようですが、私は、アリストテレス哲学がヒントになると思っています。
荒木勝先生(岡山大学副学長)という、日本におけるアリストテレス研究の第一人者の先生がいらっしゃいまして、その先生がアリストテレス「政治学」の一節を、次のように訳されています。
「実践的生活は、ある人々が考えているように必ず他人と関係を持たねばならないというものではなく、また思考にしても、実践することから生じるもののためになされる思考だけが実践的なものとは限らないのであって、むしろ自己完結的で自己自身のためにする観察(テオリア)や思索の方がはるかにより実践的なのである。」(荒木勝「アリストテレス『政治学』第7巻」岡山大学法学会雑誌 第52巻第1号 p67~p68)
これを、荒木先生の教えに従ってかみくだいていうと、こういうことになります。アリストテレス哲学の基本には「実践」があるのですが、自分で振り返ることのほうがより「実践的」だと、アリストテレスは言っています。実践をするときには、判断をしないといけない。判断の基準をきちんとすれば、実践をして、成果をうむことができる。一番大事なことは、判断の基準となっているものが、いかに公平で普遍的なものであるかということです。それが保障されていないと、判断をして実践をしても、お客様、社員、株主など周囲の人々からは喜ばれない。
このアリストテレス的な実践を行っていくにはどうしたらいいのか。自分の考えが普遍的で公平なものであるかどうかの検証を絶えず行わなければならないけれど、そのときにできるだけ広い範囲でいろんなことを論じ合った方がいい。しかも違う分野の方と対話をするととても有効です。そうなればコーチングの領域ではなく、メンタリングの領域になります。コーチングは、「あなたの判断が正しい」という前提で成り立ちますので、あらかじめ、メンタリングで、広い視野に立った公正な判断力を身につけてもらったほうが望ましいです。グローバルな見識をもったリーダーを育てようとすれば、企業はメンター制度のほうをとるだろう、と私は思っています。
留岡 メンター制度は可能性が大きいと考えていいわけですね。
松下 そうです。メンターの方はそれだけの経験を積んでいるわけですから。メンターとしてふさわしいのは、ビジネスの体験を積まれて、人間的に豊かな方です。また、メンターは一人でなく、何人か持ったほうがいいですね。
チューター制度との違い

留岡 日本企業の場合はそこが混乱していて、チューターなのか、メンターなのか。職場の先輩をメンターとしてアサインしたけれど、まったく機能していない、ということも起こり得ます。少なくとも職場が違っていることは必要だと思うのですが。
松下 新入社員のメンターだったら、同じ職場の4、5歳上の先輩のほうがいいと思うんですよ。新入社員が対象の場合は、まず、企業に慣れるということが主な目的になります。それほど広い視野もいらないのですが、課長、部長クラスになってくると、そうはいかなくなってきます。判断業務が入ってきますから。
留岡 POLARISとしてやっていきたいことの一つは、まず、メンター制度をきちんとした形で理解してもらう。薬と同じで、効用はコーチングとメンタリングで別だと思うので、「使用上の注意」をよくわかってもらった上で、使っていただく。そういうことをやってみたいですね。
松下 メンター制度とコーチングは、両方とも、1対1の人材育成の手段であることは間違いがありません。ただ、1対1の人材育成の方法は、長い間、あまり研究されてきませんでした。集合研修的なものというのは、日本に近代の学校制度ができて以来、ずっとやってきているわけですが、1対1の教育というのは、学校教育においても企業内においてもほとんど行われてきていません。それだけに、今後大きな可能性を秘めた分野だと思います。メンター制度とコーチングはそれぞれ特徴があると思いますので、それぞれの長所を生かす形で棲み分けをしていけるといいですね。
留岡 コーチングについてもメンター制度についても、大きな示唆をいただきました。ありがとうございました。
(2012年4月4日、東京・品川にて)
松下信武(まつした・のぶたけ)
1944年12月、大阪生まれ。1970年3月、京都大学経済学部卒業。2004年6月、㈱ ベルシステム24 執行役員・総合研究所長に就任。2006年2月、トリノオリンピックに日本電産サンキョー ㈱ のスケート部のメンタルコーチとして参加。同年3月、㈱ ベルシステム24 執行役員・総合研究所所長兼教育アドバイザーに就任。2007年4月~2010年3月、獨協大学経済学部特任教授。2008年10月、ゾム株式会社 代表取締役社長に就任。2009年2月、丸子修学館高校野球部のメンタルコーチに就任。2010年2月、バンクーバーオリンピックに日本電産サンキョー・スケート部のメンタルコーチとして参加(スピードスケート男子500メートルで長島選手銀メダル、加藤選手銅メダル、女子500メートル吉井選手入賞)。2010年4月、JOCオリンピック強化スタッフ、日本スケート連盟スピードスケート強化スタッフに就任。2012年3月、「わくわく元気会」コーチング品質保証コミュニティーのリーダーに就任。詳細プロフィールはこちら
著書に『EQコーチングスキル』(共著、あさ出版)、『エグゼクティブ・コーチング』(共著、プレジデント社)、『凡人が一流になる「ねたみ力」』(ソフトバンク新書)など多数がある。