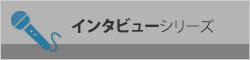鶴見道昭さんは、僕(留岡)がソニーヨーロッパ(ロンドン)に駐在していた頃に同社の社長をされていた方です。現在もロンドンにお住まいです。僕がソニーを辞めた後もご指導をいただく機会が何度もあり、グローバルインタビューシリーズの第一回は、東京出張中の鶴見さんにお願いすることにしました。
*
鶴見道昭(Michiaki “Mike” Tsurumi)さんプロフィール
Across Associates パートナー/コンサルタント。Deloitte 社外コンサルタント。
1964年慶應義塾大学法学部法律学科卒。ソニー入社 2年後にソニーアメリカ赴任。以後北米19年、欧州12年新規ビジネス開拓、顧客本位のマネジメント、チャンネルマーケティングから販売会社の経営一般を広く担当し2001年本社常務取締役。2002年には欧州ソニー社長として構造改革とビジネ スの拡大に取り組んだ。また製造業以外にも放送事業、インターネット事業の経験もある。ブランドの確立、競争と成長戦略、異文化環境下の経営、業務用と一 般民生用ビジネスなど幅広い経験で現在は数社のイギリス、アメリカ系の会社のボードメンバーやアドバイザーとして活動。また大学生のインターンシップを通じて自己啓発をする世界的団体アイセックのアドバイザリーグループのメンバーとして学生のコーチングも行っている。
*
◆ソニーアメリカに投げ込まれる
――ソニーに入社されて2年後の1966年にはソニーアメリカに赴任されていますが、海外勤務は入社のときから予想されていたのでしょうか。
僕の家庭は親父が外交官で、兄弟はみな海外で生まれています。すぐ上が11歳離れていますが、そうした年上の兄弟たちが、僕が子供の頃に家でよく外国の話をしていました。それを聞きながら育ったので、海外への関心はもともと強いほうでした。「俺も外に出てやってみようか」と思っていたので、入社前にも海外希望は伝えていました。それが早いタイミングでかなえられたといえます。
――では、ソニーアメリカ赴任は願ったりかなったり、ですね。
でも、「ぜひ行ってこい」と送り出されて、アメリカ(ニューヨーク)に着いたら、「お前何しにきた」みたいな話で(笑)。よくあることなんですが、当時は「ポジションがクリアで、やることが予め決まっている」というわけでは全然なくて、「一人くらいこっちによこしてよ」みたいなオファーだった。それで赴任したら、「盛田さんが来たから空港に迎えに行って」とか、「テレックスでこれ打って、本社とのコミュニケーションやってよ」等々。要するに雑用係です。当時は日本人の数が20人くらいでした。現地の人(アメリカ人)も20名くらい。よき時代です。
――「雑用」から始まって、どのような仕事にシフトされたのでしょうか。
メインでかかわったのは、業務用ビデオです。家庭用ビデオが1970年代に出来る前に、すでに60年代にVTRは技術的に出来ていて、まず業務用として販売が開始されました。私はそのビジネスにかかわり始め、買い付けから、セールスから、宣伝広告まで、何でもやりました。
一般的に、業務用の高い機械をコンシューマー系に落としていく、というのが市場の一つの流れなのですが、VTRでも最初のお客さんは放送局でした。NHKが相撲をビデオにとって、もう一回流す。もう一回見られるんだと、最初はみんな驚いたものです。その後、どんどん機械を小さくして、家庭用にして、70年代にコンシューマー用の幕が開いたわけですが、私はその後もずっと業務用を担当しました。放送局のほか、学校や企業がお客さんでした。コンテンツづくりにも関わりました。マグロウヒルなどの教科書系の出版社が、それまで16ミリのフィルムで作っていた教材をビデオ化することになり、それにも関わりました。映画会社と交渉して、映画をビデオ化することも始めました。
――コンテンツ・ビジネスも含めて、業務用ビデオ・ビジネスに相当深くかかわられたわけですね。
放送局で使うビデオは、最初は大きなものでしたが、それがだんだん小さくなって、取材に使われるようになりました。取材でも、もともとは16ミリフィルムで撮影していました。フィルムだと現像する時間がかかりますが、ビデオだと撮影してすぐに流すことができます。
今では歴史的な事件として教科書にも書かれていますが、72年にニクソン大統領が、当時国交のなかった中国を電撃訪問するということがあり(ニクソン訪中)、CBSがこのときの画像をVTRで流します。それはソニーとCBSが共同で開発したビデオカメラで撮られた映像であり、以後、他の放送局もソニー製のビデオを競って使うようになりました。
このときのニューヨーク赴任は7年であり、その後サンフランシスコ支店に2年出ます。そのときは、ビデオだけでなくてコンシューマー(民生)用の商品も全部扱いました。以降も、メインは業務用のビデオ、そしてカメラ、モニターなどのビデオまわりのシステム全般で、いわゆるB to B系でした。
サンフランシスコの2年のあと、カナダに4年、またニューヨークにもどってきて4年、そこまでで北米に17年です。そのあと日本に2年いて、またアメリカに2年。アメリカの最後の方は、肩書きとしてはシニア・バイス・プレジデントやバイス・プレジデントでしたが、やはり業務用ビデオの全体を見るということが主要な仕事でした。
◆「火消し役」としてのヨーロッパ赴任
アメリカから戻って日本に4年いたのち、ヨーロッパ(ロンドン)に赴任します。45歳の頃です。業務用部門の全体を見ることを4年やり、日本に2年戻って、またロンドンへ。もう一度日本に戻り(2001年には本社常務)、それで終わりかと思ったら、再度ロンドンに戻されて、ソニーヨーロッパの社長になりました。それが2002年、60歳のときです。この時代に留岡さんとご一緒したわけです。
――この頃、業務用からコンシューマー用まで、販売だけでなく生産工場まで見られていましたよね。7つくらいの工場、ヨーロッパ中を見られていた。
ちょうどITバブルがはじけて、エレクトロニクス産業は具合の悪いときであり、ヨーロッパは2002年にユーロが流通し始めたこともあって、激変のときでした。全体的に調子が悪く、環境が大きく変わった時代でした。市場環境だけでなく、ソニーヨーロッパのオペレーションが荒れていて、「火消しで行ってくれ」というところもありました。
――日本企業のグローバル化のパターンとしては、最初は現地法人の社長を日本人がやり、そこからローカライズして現地の人が社長になる。今まだこの段階の企業も多いわけですが、ソニーの場合は、その段階を過ぎて、現地化しすぎていろいろなコンフリクトが起きた。そこに対してもういちど秩序をもたらすということで、鶴見さんが行っていろいろ整理された、という印象があります。
グローバル化、現地化という課題に対して、どこの企業でも必ず問題が起こっているはずです。それに対して、私がやった方法というのは、「簡素化する」ということです。長い時間がたつと組織は肥大化したり、重複したり、複雑化する。そして、適材適所でないということが起きてくる。必ずしも適格でない人が上に上がっていったり、ファンクションを持っていたりということがあるので、グローバル化のなかで整理をしていかなければならない。これは浄化の一つのサイクルであり、それを何度か繰り返しながら企業は伸びていきます。
ソニーも1950年代の終わりからグローバル化しているので、何十年と経っているわけです。その時代時代にフィックスさせていかなければならない。家全体の立て替えはできないけれど、増築や改築をしなければなりません。それをやりながら、日本人も伸びていくことができます。
◆グローバルリーダーのコンピテンシー
――鶴見さんご自身は、グローバルリーダーのコンピテンシーとは何であるとお考えでしょうか。
市場環境が昔と今とではかなり変わってきています。企業経営も大分変わってきているので、昔のグローバルリーダーとはまた違うリーダーが求められてきているということがあります。
昔のグローバルリーダー、というのは具体的な人物イメージで言うと、井深大さんと盛田昭夫さんです。当時は日本がこれから成長するという時代ですから、クリエイティブなものをつくって、それを世界に提供していく、市場もこれからつくり、新しいエレクトロニクス産業、新しい日本をつくっていく。彼らにはそういうパッションもあるし、哲学もありました。
もう少し一般化して言えば、ビジョナリーであること、使命感があること、人を納得させる力や人を惹きつける力があること。人間の魅力度が高いということ。
今はそういう人が少ないように思いますが、それは今の人に能力がないということでなくて、時代的な要因が大きいと思います。明治維新のときや、戦後の荒廃した時代には、ビジョナリーな人、時代を引っ張る人が出やすい。そういう人がいる時代に、私も引っ張ってもらったと言えます。
今は分業化が進んでいて、リーダーシップに専門性が出てきています。欧米の場合は、「私は会社のトップになります」と最初からマネジメントに向かうグループがいる。日本の会社のトップというのは下積みからどんどん上がっていくので、それとは少し異なります。日本の場合は、悪く言うとサラリーマン的。根回しもうまいし、協調もできる。突飛なことを言って、みんなから「こいつ変なヤツだな」と言われるような人が社長になるケースは稀です。そこで求められるコンピテンシーは、調整能力だったり、人を使う能力だったり、持っているリソースを使いながら経営を伸ばしていく能力であることが多いです。
私自身は、グローバルリーダーのリーダーシップは、もうすこし原始的にもどった方が良いなという気がしています。
――原始的というのは。また、そうしたコンピテンシーはどういう環境、どういうキャリアで育つのでしょうか。
温室育ちではだめです。環境の変化の中につっこんで、そこに対応していくといった経験をさせることがどうしても必要になってきます。日本だけでなくて海外、海外も欧米だけでなくて、中国などアジアも経験させるとか、そういう中でリーダーを育てるというのが、昔も今も変わらないのではないかと思います。
ただ、今は、エレクトロニクスや自動車のような典型的なグローバル産業の成長力が非常に弱くなってきている、という構造的な問題があります。その一方で、それ以外の産業にはこれから伸びていく力があるのではないか、まさに新しいリーダーが、そういうところで育つチャンスがあるのではないかという気がしています。
ネガティブな言い方をしてしまうけれど、海外赴任をしても、何年か外でやって帰って本社の部長になります、役員になります、黒星はつけたくないという、サラリーマン的な考え方でやっているのではだめでしょうね。むしろ、外から見ると本社の悪いところも見えるのです。それを利用して、帰ったら大きな変革を自分でやってみよう、などと全く違った発想をしてほしい。いい機会ですから、これからの人にそこをやってほしいという気がします。
確固とした大企業で、ストラクチャーができている中でやればやるほど、型にはまったプロセスに入ってしまうので、それを打破する。違う産業につっこんでしまうとか、まったく違うところに環境を変えてしまう。異文化でもイスラム教の国に入れてしまうとか。そういう、次元の違うところに入れてしまう。
――ある意味で、乱暴なことをやったほうがいいと。
僕らは乱暴な時代にいたんですよ。何の努力もしないでも、けっこういろんなことをやらせてもらえました。道なき道を行く、新しい道を拓く、といったことがすごく面白くて、魅力的でした。ところが、今はそういうことはなくなってきているから、敢えてしないと駄目なんじゃないかという気がします。
――僕(留岡)がエグゼクティブ・サーチの仕事を選んだ動機の一つでもあるのですが、乱暴に環境変化をつくりだすことができると、そこから個人の潜在能力を引き出す何か生まれるのではないかと考えています。ただ実際は、そういうことを求める人はいるのですが、そうした人材を求める会社が少ない。乱暴なことを自ら望むような志の高い人が満足するレベルの会社が、かなり少なくなってしまっている。それで、僕は、才能を活かせるチャンスの場をデベロップメントをするのが仕事と思っています。
◆ダイバーシティ感覚=周波数の違いを聞き分ける
――グローバルリーダーと国内リーダーの違いをどんなふうに考えればよいのでしょうね。たとえば、ダイバーシティ(diversity、多様性)感覚の有無というのはその大きな要素になりますか。
国内でも共通しますが、まず、価値観を持っているかどうか、というのがリーダーの資質として大きいですね。それが、グローバルにも通用する価値観であるとして、その先は、コミュニケーションの能力だと思います。その価値観を皆さんにわかってもらう、世界にわかってもらう努力をする。その際に重要なのが、世界の人の考え方をどう採り入れてやっていくのかという、「感度の良さ」とでもいうべきものです。
よく、盛田さんがこんなふうにおっしゃっていました。「あなたたちは、自分の話が聞いてもらえないとか、自分の言っていることを理解してもらえないと言うけれど、それは、聞く側の人が何を聞きたいと思っているのかということがわかっていないから。つまり、チューニングがあっていない。ラジオだって、出す周波数と受ける周波数が一緒でないと聞こえないのと同じで、周波数があっていないんじゃないの」。
ダイバーシティ感覚がある、というのはつまり、「いろいろな周波数があるということがわかっている」ということだと思うのです。わかっているから、それぞれの周波数に合うようにメッセージを出していくことができる。盛田さんが英語がうまいとかそういうことではなくて、感度のアンテナが高い上に、いろいろな周波数があるということがよくわかっていて、チューニングがうまい。だから、聞いた人が盛田さんの話に納得するわけです。
――なるほど、ダイバーシティ感覚というのは、周波数のそれぞれの違いを聞き分けるということなんですね。国内リーダーの場合は、その能力はなかなか身につかない。
国内のリーダーだと、多くの場合、日本人の持っている共通の価値観にフォーカスしますから、国内にいれば、違う周波数を聞き分けよう、それに合わせよう、という苦労はしないですんでしまいます。だからそのへんの殻を破らないと、グローバルリーダーとしては難しいといえます。
ダイバーシティというのは、人種、宗教の違いもありますし、ジェンダーの違いもあります。Chief Diversity Officer(CDO)というポジションを、一部のアメリカ企業などは置いています。彼らがやろうとしているのは、ダイバーシティを広く持つことによって、よりその企業を強くしようということ。なぜ強くなるのかというと、企業が多面性を持てば持つほど、お客さんのところにより感度良くメッセージを向けられるからです。女性をどうするか、ということも含めて、日本企業はまだそういう意識が弱いですよね。本当はそういうことへの感度が鈍い、日本こそがやらなくてはいけないんですが。
◆海外で「つらい目に遭う」ことの大切さ
――海外勤務で一皮むけ、その後、全社経営人材になるというケースがありますが、そのような“修羅場孵卵器”機能が、海外勤務にはあるととらえてよろしいでしょうか。
海外勤務の大きなメリットに、守備範囲が広がるということがあります。日本では、「私は管理だけやっていました」「セールスだけやっていました」という人でも、海外に出ると範囲が広がる。一般的に、日本よりオペレーションが小さいですから。守備範囲が広がれば広がるほど、経験値が増えていく。
たとえば、パナソニックの中村邦夫会長も、キヤノンの御手洗冨士夫会長も、現地法人のトップをされた経験をもっています。海外現地法人のトップというような全般を見る経験は、予行演習ではないけれど、ミニ社長のような経験になる。これは、ものすごく実践的なひとつのトレーニングです。
それから海外にいると、先ほど言ったような異文化、多様性を経験するとともに、日本本社そのものが見えてくる。日本本社の中にいるとわからないことが、外に出てくると、「これは、ちょっとおかしいな」と気づくようになる。そういうことがわかったうえで、経営者になっていったほうがいいでしょう。同じところで純粋培養されてしまうと、どうしても自分の世界が狭くなってしまう。
――純粋培養を避けるには、海外に出て、自分の会社を客観視できるようになったほうがよいと。
客観視できるようになる、ということもあるのですが、異文化経験など、いろいろな「つらい目」に遭うことには、非常に大きな学習効果があります。つらい目に遭うことは、自分の血となり肉となる。つらい経験をした人、そういうDNAを持った人たちを増やしていくということが、会社としても、実はとても大事なのです。表面上は目立たないかも知れないけれど、見えざる所に強さがでてくる。会社というのは売上規模や利益規模などでみんな判断しがちだけれど、そういう人たちがどれだけいるか、というのが強さの源泉なのです。
いま、韓国、中国、インドにそういうポテンシャルを持った人がたくさん出てきています。これは、表面上は数字に出てこないけれども、何年か経ってみたりすると、日本と大きな差になって出てくるという恐れがあります。
ですから単純に、「日本人に高いお金を使って現地に送り込むよりは、現地人でやったほうが安くできるし効率的だ」と考えたらだめでしょうね。
――最近海外勤務をされた方から伺ったのですが、最近は、本社が「やれシェアがどうだ」とか細かく言うようになってきて、仕事のうちの7割くらいは本社を向いて仕事をしているようになってきている、と言うんですね。本当は競合とマーケットを見て仕事をしないといけないのに。そういう反応が出てきているので心配しています。今おっしゃった、「つらい目に遭う」とか学習効果が大事なのに、つらい目というのは、「本社からのつらい目」だけ。
海外に赴任したからには、日本でやってきたことを解脱すること。本社がこう言っているからと、本社を向いて仕事をするようでは駄目なんですよね。いくら本社がぐちゃぐちゃ言っても、現地、そこでのお客さん、現場、そこの人たちを代表して、「だからこういうふうにしたいんだ」ということを、本社側にどんどんぶつけていく。
本社官僚が強くなるという傾向は、グローバル化の進展とともに出てくるでしょう。グローバル化が進めば進むほど、そういう組織形態をつくっておかないと、どんどん分裂してしまうんじゃないか、遠心力でコントロールが利かなくなるから、グリップを強くしたいと考えると思うんですよ。それはしょうがないのですが、それに打ち勝つだけの力をローカルで持っていないといけない。
立場が上になると本社に対しても言えるけれども、若い人だと言えない、考えられない、ということがあるから、そのへんはコーチングの役割だと思います。
――それを僕(留岡)も思っていまして、かつてのように海外で自由にならないので、精神的支援と成長支援にコーチングが入っていくと、より良いのではないかなと。本人に「サポートが必要だ」という自覚がある場合は、個人としてコーチを頼んでくるのですが、自覚がない場合も多いので、そういう場合は会社の人事担当者が、システムとしてコーチングを採り入れてくれれば、と思っています。ただ、最近人事の方と話していて、あまり「成長支援」を考えていないのでは、と思わざるをえないこともあります。風切り羽を抜いたくらいのフラミンゴにしておきたい、というような(笑)。
◆純粋培養は危険
――個人にとどまらず、これまでグローバルでなかった企業や産業も、グローバルに出て「つらい目に遭う」ことが、成長していくうえで必要なのかも知れませんね。
一つの問題は、国内で成功しているところは、外に出る理由がないということです。一方で、自分の事業やあるいは産業自体が、国内ではもうだめだ、外に自分で打って出ないと将来がないなと思ってそこで一気にやれば、できると思います。日本の外に出て行って、がちゃがちゃやって、力をつけていけばいい。「俺は歯をくいしばって、そういうところに出て行ってやってやろう」「こんなところで甘っちょろい汁をすっていたってだめだ」と思う若者や、30代、40代が頑張ってくれたら、日本全体として変わってくると思います。規制で守られている国内だけにいると、純粋培養で「もやし人間」になってしまう。純粋培養は、人だけでなく、企業も国も弱めてしまう。
――新しい潮流として、たとえば、セキュリティ会社のセコムなどが、イギリスなどでかなりいろいろな試みをやっていますよね。
海外で、日本のセコムと同じやり方でセキュリティを提供しようとすると、「この国では、そんなことは過剰サービスですよ」と最初は言われる。でも、本当にやってみたら、お客さんが喜ぶんだそうです。日本人は顧客の要求レベルが高い。日本の強さは、顧客の要求度が高いことともいえます。サプライヤー側は、その要求にミートするだけのサービスをつくらなければなりません。それは、下手すると過剰サービスであったり、過剰品質であったりするわけですが、日本国内だけに通用するものと思い込んでいたら、海外でも本当は求められているという可能性もあります。
実はそういったモノやサービスは、日本に沢山あると思います。東京や関西に限らず、地方にも。地方の産業で、本当にグローバルに競争力のある「モノ」があるのだとしたら、あとは「ヒト」の問題ですね。グローバル人材をどうやって育てるかという。まさに留岡さんのご専門の部分です。
――鶴見さんはいまイギリスにおられて、イギリスから日本、とくに鳩山新政権下の日本はどのように見えますか。
友愛も平等もいいけれど、それだけではだめでしょう。また、「大企業が悪い」「グローバル化が悪い」という風潮にもたいへん疑問です。自動車、電機というのは、今まで海外でやたらと叩かれてきた。だから、ものすごくコンペティティブなのです。大企業が悪い、グローバル化が悪い、と言われているけれど、グローバルでこれだけ頑張ったから、今日の日本があるのであって、そんなことを言っていたら、日本の将来はないですよ。大企業=悪なわけではなくて、評価すべきところは正しく評価して、中小も含めてこれから頑張ろうじゃないか、国内事業にだけ引っ込んでいないで、海外に出て頑張れとか、そのために規制をなくそうとか考える方が、国のためと思います。
――僕も、最近はやりの「ナンバーワンよりオンリーワン」という言い方が嫌いで、「グローバルトップ3にならないと生き残れない」と思っています。でも、あるところで、「オンリーワンよりナンバーワン」と言ったら、顰蹙を買いまして(笑)。
日本全体にチャレンジングな精神がなくなってきてしまったように見えることが心配ですね。みんながしらけてきちゃったように見えます。日本は経済成長して、量的に拡大したけれど、質的な向上が追いついていない。平均的な生活水準は改善したものの、みんながハッピーというわけではない。お父さんが頑張って仕事をして年から年中働いてきたけれど、リストラされちゃった。大企業で働いても意味はない、云々と。
それで、我々の世代が一生懸命がんばってお金を稼いで、子供たちに良い教育をさずけたのに、挙げ句の果てに、その彼らがフリーターになってしまった。そうなってしまったとしたら、我々は何のためにやってきたのか。「お前ら、もう食わせないぞ。とっとと出て行って働いてこい」と、昔はそのくらい言っていたわけですが。
◆世界を入れる/世界に入る
――アイセックに関わられているのは、グローバルな若者を育てたいというお考えからでしょうか。
アイセックは海外インターンシップ事業などを行う、学生が運営するグローバル非営利組織ですが、私はメンター役として関わっています。彼らを育てたいというのもあるし、彼らから触発されたいということもあります。もともとの私の問題意識は、そういうグローバルな活動のなかに、そもそも日本人が少ないということです。中国やインド、東欧などの学生は、そうした活動もどんどんやっている。次のジェネレーション、潜在力のある若いジェネレーションのグローバル度が、日本は1周遅れでなくて、3周、4周遅れという危機感があります。
実は、日本の学生がアイセックなどの活動をしたがらない理由には、就職するときに結局、企業が異質なものをとりたがらないということがあります。企業の方が、「そんな活動はしないで日本で勉強だけしてきてくれれば、あとは企業のなかでトレーニングするから」というような意識でいて、それが学生にも伝わってしまっている。海外で一年間何かやってきたとか、どこかの会社でインターンで働いたことがあるという人は、大きな成長をしてきている。そういう人をとれば、本当は会社にとってものすごく役に立つのだけれども、それをいやがる。まっさらで画一的なら、あとは会社が色をつけられるからいい、と。
――尖った人が入ってきたときに、採用したはいいけれど、すぐに辞めたりすると、採用した人間の減点になる、ということがあります。だから企業が、辞めそうになくて、従順で、ほどよくその企業に染まる、という人を採用しがちというのはわかります。かつてソニーで、盛田さんなどの言葉で驚いたのは、社員に「辞めていいよ」と言っていたことです。つまり、「お前、売れる人材(salable)になっているか?」と。そういうメンタリティが、いまは企業の上のほうの人たちにあまりないように感じます。そういう環境があるだけでも、人が育つと思うのですが。
その通りですね。そして尖った人、海外経験のある人が企業に入ったときに気をつけなければいけないのは、せっかくそういう貴重な経験、「世界を入れる」経験をしてきているのに、それを小さくとらえてしまうこと。たとえば語学屋さんになってしまうというパターンがあります。
たまたま、海外経験があって英語ができるというような人がいると、「こいつの英語力を使って、翻訳、通訳させよう」とかいうことになる。それはグローバリゼーションではありません。英語ができる人を、異質に思ってしまう。日本人は同質化を、カンファタブルに感じるから、グローバルな要素を、異質なものとして排除してしまう。
――僕は「世界を入れる」というときに、個人として世界を自分の内側に入れるということと、移民を日本の国に入れる、というのと、両方の意味をイメージするのですが、移民についてはどうお考えですか。
島国で、世界から切り離されて、平和に小さく生きるのがいいのか、それとも、もっと開放して、異種交配をさせることがよいのか。私は後者だと思います。ダーウィンは、異種交配をして、適者が残っていく、ということを述べました(適者生存)。青白い顔をした日本人ばかりだと、いずれ平和に亡びてしまうのではないか。そんな危惧をもっています。
――だんだんとお湯の温度が上がっていっていることに気がつかなくて死んでしまう「ゆでガエル」のたとえは、本当に日本のことではないかと思ってしまいます。
自分で気がついていないということが、いちばん怖いですね。
◆黄金世代のグローバル経験をどう生かすか
――鶴見さんは、「Made in Japan」とともに「世界」を身中に入れ得た黄金世代の代表の一人だと、僕は思っています。「黄金世代」というのは、鶴見さんたち60歳以上の方々というイメージですが、その方々と会っていると、問題意識も違えば、経験値も全くわれわれの世代と違う。たとえば、ブラジルに工場を立ち上げたという人は、土地の買い取りから始めています。この世代の方々がいま何を考えているのか非常に興味があると同時に、われわれ40代はブリッジにはなれるかな、という思いがあります。問題意識の高い20代・30代と、経験値の高い60代。U字型の上と上をつなぐ役割を、僕自身も果たしたいと思っているのですが。
僕は、ある意味でロストジェネレーションではないかと思うんです。たとえば、就職して最初にアメリカに行った頃にビートルズが流行っていたな、というのはうっすらと覚えているのですが、以後、日本やアメリカの歌手で誰が流行っていた、という記憶は喪失している。なぜかというと、そういうことにかまっていなかった。これからの市場をどうやってつくっていくとか、そういうことに没頭していたので、ずっと戦地で戦っていた兵隊みたいなもので(笑)。終戦を知らずに30年間フィリピンのジャングルにいて日本に帰還した小野田寛郎さんみたいな状態です。だから、当時見過ごした映画を見ようとか、流行っていた音楽を聴こうとか、失われた記憶を取り戻すのが、これからの楽しみでもあります(笑)。今の60代・50代にはそういう経験者が非常に多いと思います。
――20年、30年、ずっと没頭されていたということなんですね。しかも、その没頭した対象がグローバルな市場だった方々の経験値というのは、そうとう濃い。
僕たちは今ここで勝たないと、と思って必死になって戦ったジェネレーションなんだけれど、今の人たちは、「けっこう勝ってるじゃん。別にドンパチ戦わなくても、侵略されるわけじゃないし」と思っている可能性があります。どうしたら、彼らはエキサイトし、チャレンジするのか。日本が立ち行かなくなって、海外に出て行くことが死活問題になれば違うけれど、そうはならないので。
ですから、僕らの持っているノウハウとか経験値を大いに使ってほしいけれども、本当に使ってもらえるのかな、という思いもあります。数は少なくてもいいけれど、尖った人が何人か出てきて、そういう人たちが引っ張ってくれるといいですね。アイセックの学生たちにも、「あなたたちは敢えてリスクをとり、敢えて新開地に足を踏み入れてほしい」と言っています。はっぱをかけたり、なだめすかしたり、インセンティブを与える、ということを常にやらないといけない。
これからのグローバル化はどんな産業でもよいのですが、そこには必ず、リーダーがいないとダメなんですね。そういう哲学をもった人がいないと。
――ひとつ思っているのは、過去、超ドメスティック産業だったところがグローバル化するときに、製造業でグローバルの経験を積んだ人が、トランスファーされていくとよいのではないかと。そうしたことは今後進むでしょうか。実際に、旧来のグローバル産業から、新たにグローバル化しようとしている産業に行った人を知っているのですが、実はあまりうまくいっていない例もあります。
これからは、産業間のグローバル人材のシフトは、十分ありえると思います。ただ、新しい産業に入るということと、グローバル市場で戦うということは、二つの意味のチャレンジです。だから、相当覚悟を決めて、歯をくいしばってでもやるということでないと、「こんなんじゃやっていられない」ということになってしまう可能性がある。大企業で甘やかされて育った場合、新たな産業でちょっとハードなことをやらせると、ついていけない、ということもあるのかもしれません。
(収録・2009年11月2日)